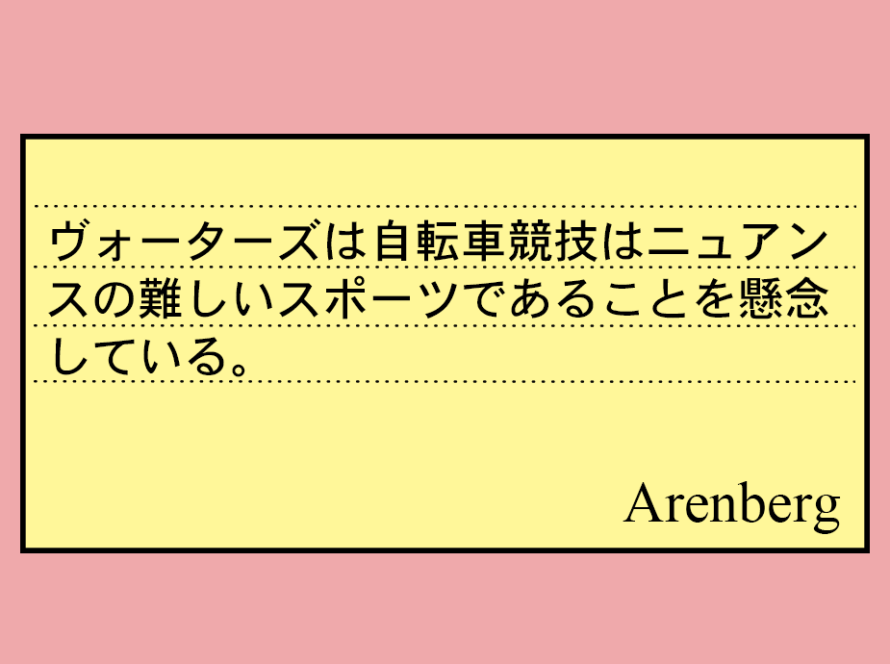本稿は、2017年にウェブメディア「産経Cyclist」へ書評として寄せたもの。様々な自転車情報が集まる総合サイトとして価値あるメディアだったが、残念ながら更新を停止。過去記事も消滅した。現在は動画による情報発信にシフトしている。

『俺たちはみんな神さまだった』(ベンヨ・マソ著、安家達也訳、未知谷)
偉大な作家であり釣り師であった故開高健は、釣りに行けず書斎で釣りに関する書物にふけり水辺に思いを馳せる釣り師を、アームチェア・フィッシャーマンと呼んだ。窓の外に寒風吹きすさぶ冬は、ゆっくりと読書の中に自転車を探すのもいい。さしずめ、アームチェア・サイクリストといったところだろうか。安楽椅子に腰掛けながら、頭の中ではペダルを回している。
ショートスリーブのジャージとショーツで走らなくなって久しいこの時節は、灼熱の太陽に照らされたサイクリストの姿が恋しくなる。ツール・ド・フランスの鮮やかな色彩を活字に求め、手に取ったのは『俺たちはみんな神さまだった』(ベンヨ・マソ著、安家達也訳、未知谷)だった。しかしここにはヒマワリに象徴される真夏のフランスの艶やかさも、ヴァカンスの陽気も、広く青い空もない。ここで語られるのは、苛烈さや峻厳さであって、真冬の今の方がよっぽど地続きになっていると錯覚するほどのフランスの7月。匂い立つものは夏草の青いきれではなく、愛おしくなるような人間臭さだった。ぐいぐいと活字に引き込まれていく。
本書の舞台は、1948年のツール・ド・フランス。今から70年前のツールを最初から最後まで追いかけたドキュメンタリーだ。オランダ人の社会学者である作者のベンヨ・マソは、この1948年のツールを「近代ツール」の始まりの年として定義している。1997年に今中大介さんが日本人として初めてツールに出場することが決まったとき、歴史に隠れていた「本当に初めてツールを走った日本人」川室競の存在にもスポットライトが当てられた。後に今中さんは、「近代ツール初」の日本人と形容されたが、その近代とは何か? ずっと疑問に思っていた。
一般的な定義であれば、第二次世界大戦が前近代と近代を分ける境界になるだろう。それは1903年に始まったツールに7年間の中断を余儀なくさせたのであり、1947年の再開から今日に至るまでツールは1年も休まずに続いている。マソがこの1947年ではなく、その1年後の1948年を近代ツールの始まりとしたのは、「最後のステージだけとはいえ、この競技を決定的に変えることになるテレビ放送が行われた」のが理由に挙げられている。ツールが始まっておよそ半世紀の間は、ツールとはテレビの生放送で見るものではなく、沿道で直に、あるいは新聞紙面で見るものだったということだ。
今日では日本でもツールは生で見られる(がために7月の睡眠不足者が続出している)が、これは観る側がレースを判断できるということである。どこで誰がアタックしたか、どこで誰が脱落したか、どんな駆け引きがあったか。しかし1948年次点では、ほぼリアルタイムの選手の映像を見ることはできず、ファンは新聞記事やラジオを通じてレースを知るのだった。言い換えればジャーナリストの果たす役割が大きい時代だった。
1944年生まれのマソはもちろんこのツールをリアルタイムで経験したわけではない。だからこそ、丹念な取材を積み上げて多くの素材を得て、多面的に1948年ツールを浮かび上がらせようとする。こうした手腕は社会学者である氏の得意とするところだと思われるが、毎日のステージの単なるレース結果の羅列とは違って、選手たちの葛藤や怯え、欺瞞、利害関係などの人間味あふれる日々のレポートは読み物として秀逸だ。
いくつか本書で取り上げられた面白いエピソードを紹介しよう。当時のツールは国別対抗チーム戦で、現在の世界選手権のような趣があった。夜行列車でフランスへやってきたイタリアチームだったが、おしゃべりすぎるエースのジノ・バルタリが一晩中騒いでいてチームメイトはほとんど眠れなかったこと。この時代のツールでは毎日総合最下位の選手が自動的にレースから排除されること(!)。総合最下位から2番目にいる選手も、レース中に最下位の選手がリタイヤしたら彼がレース後に失格となるため油断はできない。レースも終盤の第18ステージでは、総合最下位のボナベントゥールがどうせ排除されるならと自らレースを止めようとするのを、自身の立場を危ぶんだ最下位から2番目のセゲッツィが慌ててレースを続けてくれとボトルを渡してまで懇願したこと。走り続けることを選んだボナベントゥールが、今度はセゲッツィのパンクを目の当たりにして、総合最下位から脱することができるかもしれないとアタックを仕掛けたこと。そして窮地に陥ったセゲッツィを助けアシストを買って出たのが、マイヨ・ジョーヌを着る偉大なチャンピオン、ジノ・バルタリだったこと……。毎日がドラマに満ちたツールの3週間がこうしたエピソードの密度もたっぷりに語られる。
選手たちのユーモラスな側面が語られる一方で、非人道的な気象条件とコース設定、そしてそれを生き抜いてきた選手たちには伝説の時代の残り香も感じられる。現代のロードサイクリングのマーケットには「エピック」とか「冒険的」というフレーズが溢れているが、サイクリングにおいてそれが本当はどんな意味を持っていたのかを、この本を読めば感じられるかもしれない。
データや分析に基づいた戦略、チームへの徹底的な忠誠の上に組織される現代ロードレース(この本が出版された2003年から2018年の今日に至る15年の間にも驚くほどの変化があったのは皆さんがご存知の通りである)を観ていると、この本で語られるレースははるか大昔の別の世界の出来事のようにすら思えてくる。しかし、1920年代に自転車選手たちを呼んだ「路上の囚人」というフレーズが、今なおフランスでは使われ続け、そしてそれを見事な形容だと思うとき、ツール・ド・フランスの連綿と続く歴史が息づいていることを実感する。
この先もツールを見たいファンはたくさんいると思う。なにより私自身がそうである。そして現在は、あらゆる情報が波のように押し寄せてくる時代である。もはやジャーナリストだけでなく、スタッフそして選手がどんどんツールの現場から声を発信している。情報過多(情報に過多などないのかもしれないが……)な現代だからこそ、ハードカバーに綴じられた活字でじっくりとツールを読んでみてはいかがだろうか。ツールがなぜ100年以上も続いているのか、ヨーロッパでツール・ド・フランスという現象がどう受け入れられてきたか、丹念な取材と上質な記事が明かしてくれる。
何より、毎日のステージをテンポの良い文章で読み進めていくスリルが一冊の本として楽しめる。70年前の7月に思いを馳せながら、アームチェアに沈みながら読んでみてはいかがだろうか。